靴底のすり減り補修ゴムが交換時期になってきたので交換してみました。
この記事では、ニューキストやSUMCOなどのスニーカーや革靴の踵(かかと)やつま先に貼り付ける補修プレートを交換するための剥がし方と貼り付け方を記載しています。
※自分の靴に合う補修プレートのサイズや色をお使いください
- 掃除
- 消臭
- 水
- カード
- デバイス
 ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,000新品最安値 :¥1,000
ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,000新品最安値 :¥1,000 ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥549 (¥14 / 個)新品最安値 :¥398 (¥10 / 個)
ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥549 (¥14 / 個)新品最安値 :¥398 (¥10 / 個) Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 2022年03月04日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,436
Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 2022年03月04日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,436 使い捨てクロス発売日 : 2024年01月17日価格 : ¥1,408 (¥22 / 個)新品最安値 :¥1,408 (¥22 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 2024年01月17日価格 : ¥1,408 (¥22 / 個)新品最安値 :¥1,408 (¥22 / 個) フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2020年09月05日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,408
フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2020年09月05日価格 : ¥1,436新品最安値 :¥1,408 Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,180新品最安値 :¥1,180
Home & kitchen - AmazonGlobal free shipping発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥1,180新品最安値 :¥1,180 ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2016年09月22日価格 : ¥841 (¥26 / 個)新品最安値 :¥780 (¥24 / 個)
ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2016年09月22日価格 : ¥841 (¥26 / 個)新品最安値 :¥780 (¥24 / 個) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン ホーム・日用品発売日 : 2021年10月18日価格 : ¥1,797 (¥150 / 個)新品最安値 :¥1,797 (¥150 / 個)
ホーム・日用品発売日 : 2021年10月18日価格 : ¥1,797 (¥150 / 個)新品最安値 :¥1,797 (¥150 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2025年09月10日価格 : ¥525 (¥44 / 個)新品最安値 :¥525 (¥44 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 2025年09月10日価格 : ¥525 (¥44 / 個)新品最安値 :¥525 (¥44 / 個) ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2019年04月12日価格 : ¥833 (¥35 / 個)新品最安値 :¥810 (¥34 / 個)
ワイパー・ダスター取替シート発売日 : 2019年04月12日価格 : ¥833 (¥35 / 個)新品最安値 :¥810 (¥34 / 個) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2022年03月25日価格 : ¥717 (¥4 / 個)新品最安値 :¥658 (¥3 / 個)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2022年03月25日価格 : ¥717 (¥4 / 個)新品最安値 :¥658 (¥3 / 個) フロアモップ・フロアワイパー
フロアモップ・フロアワイパー フロアモップ・フロアワイパー
フロアモップ・フロアワイパー 高級筆記具ストア パーソナル発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥692新品最安値 :¥692
高級筆記具ストア パーソナル発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥692新品最安値 :¥692 使い捨てクロス発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥439 (¥110 / 個)新品最安値 :¥439 (¥110 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥439 (¥110 / 個)新品最安値 :¥439 (¥110 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2025年06月01日価格 : ¥888 (¥7 / 個)新品最安値 :¥888 (¥7 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 2025年06月01日価格 : ¥888 (¥7 / 個)新品最安値 :¥888 (¥7 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2018年08月01日価格 : ¥391 (¥4 / 個)新品最安値 :¥391 (¥4 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 2018年08月01日価格 : ¥391 (¥4 / 個)新品最安値 :¥391 (¥4 / 個) 使い捨てクロス発売日 : 2023年09月22日価格 : ¥1,056 (¥3 / 個)新品最安値 :¥1,056 (¥3 / 個)
使い捨てクロス発売日 : 2023年09月22日価格 : ¥1,056 (¥3 / 個)新品最安値 :¥1,056 (¥3 / 個) フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2015年05月01日価格 : ¥477新品最安値 :¥398
フロアモップ・フロアワイパー発売日 : 2015年05月01日価格 : ¥477新品最安値 :¥398
 ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2018年10月01日価格 : ¥797 (¥1 / g)新品最安値 :¥773 (¥1 / g)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2018年10月01日価格 : ¥797 (¥1 / g)新品最安値 :¥773 (¥1 / g) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2013年09月27日価格 : ¥251 (¥13 / ml)新品最安値 :¥251 (¥13 / ml)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2013年09月27日価格 : ¥251 (¥13 / ml)新品最安値 :¥251 (¥13 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,182 (¥1 / g)新品最安値 :¥2,182 (¥1 / g)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,182 (¥1 / g)新品最安値 :¥2,182 (¥1 / g) ホーム・日用品発売日 : 2024年10月27日価格 : ¥1,178 (¥47 / g)新品最安値 :¥1,178 (¥47 / g)
ホーム・日用品発売日 : 2024年10月27日価格 : ¥1,178 (¥47 / g)新品最安値 :¥1,178 (¥47 / g) 置き型発売日 : 2016年03月12日価格 : ¥510新品最安値 :¥510
置き型発売日 : 2016年03月12日価格 : ¥510新品最安値 :¥510 ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年02月27日価格 : ¥268 (¥1 / ml)新品最安値 :¥248 (¥1 / ml)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年02月27日価格 : ¥268 (¥1 / ml)新品最安値 :¥248 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2023年11月12日価格 : ¥1,649 (¥65 / ml)新品最安値 :¥1,649 (¥65 / ml)
置き型発売日 : 2023年11月12日価格 : ¥1,649 (¥65 / ml)新品最安値 :¥1,649 (¥65 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年09月13日価格 : ¥1,130 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,130 (¥1 / ml)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年09月13日価格 : ¥1,130 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,130 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2017年09月15日価格 : ¥548新品最安値 :¥488
置き型発売日 : 2017年09月15日価格 : ¥548新品最安値 :¥488 置き型発売日 : 2022年12月31日価格 : ¥1,118 (¥1 / g)新品最安値 :¥1,118 (¥1 / g)
置き型発売日 : 2022年12月31日価格 : ¥1,118 (¥1 / g)新品最安値 :¥1,118 (¥1 / g) 置き型発売日 : 2024年04月19日価格 : ¥1,215 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,203 (¥1 / ml)
置き型発売日 : 2024年04月19日価格 : ¥1,215 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,203 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年11月03日価格 : ¥822 (¥274 / 個)新品最安値 :¥822 (¥274 / 個)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年11月03日価格 : ¥822 (¥274 / 個)新品最安値 :¥822 (¥274 / 個) 置き型発売日 : 2025年09月29日価格 : ¥252 (¥1 / ml)新品最安値 :¥252 (¥1 / ml)
置き型発売日 : 2025年09月29日価格 : ¥252 (¥1 / ml)新品最安値 :¥252 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年10月01日価格 : ¥591新品最安値 :¥591
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2017年10月01日価格 : ¥591新品最安値 :¥591 ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2016年04月11日価格 : ¥1,106 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,106 (¥1 / ml)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2016年04月11日価格 : ¥1,106 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,106 (¥1 / ml) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2020年01月17日価格 : ¥1,130 (¥2 / g)新品最安値 :¥1,130 (¥2 / g)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2020年01月17日価格 : ¥1,130 (¥2 / g)新品最安値 :¥1,130 (¥2 / g) 置き型発売日 : 2017年07月20日価格 : ¥509 (¥3 / g)新品最安値 :¥478 (¥3 / g)
置き型発売日 : 2017年07月20日価格 : ¥509 (¥3 / g)新品最安値 :¥478 (¥3 / g) ゴミ箱用アクセサリ発売日 : 2025年03月06日価格 : ¥870 (¥24 / g)新品最安値 :¥870 (¥24 / g)
ゴミ箱用アクセサリ発売日 : 2025年03月06日価格 : ¥870 (¥24 / g)新品最安値 :¥870 (¥24 / g) ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年10月04日価格 : ¥1,770 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,770 (¥1 / ml)
ソフランプレミアム消臭_100円OFF| ライオン発売日 : 2021年10月04日価格 : ¥1,770 (¥1 / ml)新品最安値 :¥1,770 (¥1 / ml) 置き型発売日 : 2020年03月01日価格 : ¥563新品最安値 :¥150
置き型発売日 : 2020年03月01日価格 : ¥563新品最安値 :¥150
 ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,826 (¥118 / 本)新品最安値 :¥2,826 (¥118 / 本)
ジャンル別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥2,826 (¥118 / 本)新品最安値 :¥2,826 (¥118 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,252 (¥52 / 本)新品最安値 :¥1,252 (¥52 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,252 (¥52 / 本)新品最安値 :¥1,252 (¥52 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥300 (¥38 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥300 (¥38 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥1,620 (¥68 / 本)新品最安値 :¥1,500 (¥62 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月24日価格 : ¥1,620 (¥68 / 本)新品最安値 :¥1,500 (¥62 / 本) 炭酸水発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,448 (¥60 / 本)新品最安値 :¥1,448 (¥60 / 本)
炭酸水発売日 : 2021年04月13日価格 : ¥1,448 (¥60 / 本)新品最安値 :¥1,448 (¥60 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月25日価格 : ¥1,220 (¥136 / 本)新品最安値 :¥1,220 (¥136 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2023年04月25日価格 : ¥1,220 (¥136 / 本)新品最安値 :¥1,220 (¥136 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年01月01日価格 : ¥1,176 (¥131 / 本)新品最安値 :¥1,176 (¥131 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2025年01月01日価格 : ¥1,176 (¥131 / 本)新品最安値 :¥1,176 (¥131 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年10月05日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2021年10月05日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本) 炭酸水発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥1,712 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,712 (¥71 / 本)
炭酸水発売日 : 2025年09月18日価格 : ¥1,712 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,712 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2023年05月03日価格 : ¥1,071 (¥119 / 本)新品最安値 :¥1,071 (¥119 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2023年05月03日価格 : ¥1,071 (¥119 / 本)新品最安値 :¥1,071 (¥119 / 本) 炭酸水発売日 : 2022年04月04日価格 : ¥1,680 (¥70 / 本)新品最安値 :¥1,680 (¥70 / 本)
炭酸水発売日 : 2022年04月04日価格 : ¥1,680 (¥70 / 本)新品最安値 :¥1,680 (¥70 / 本) 炭酸水発売日 : 2020年02月03日価格 : ¥2,266 (¥94 / 本)新品最安値 :¥2,266 (¥94 / 本)
炭酸水発売日 : 2020年02月03日価格 : ¥2,266 (¥94 / 本)新品最安値 :¥2,266 (¥94 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2022年07月05日価格 : ¥1,698 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,698 (¥71 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2022年07月05日価格 : ¥1,698 (¥71 / 本)新品最安値 :¥1,698 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年05月27日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2025年05月27日価格 : ¥1,107 (¥123 / 本)新品最安値 :¥1,107 (¥123 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2018年05月22日価格 : ¥1,999 (¥83 / 本)新品最安値 :¥1,700 (¥71 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2018年05月22日価格 : ¥1,999 (¥83 / 本)新品最安値 :¥1,700 (¥71 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月06日価格 : ¥1,476 (¥164 / 本)新品最安値 :¥1,476 (¥164 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2021年04月06日価格 : ¥1,476 (¥164 / 本)新品最安値 :¥1,476 (¥164 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2021年02月05日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2021年02月05日価格 : ¥864 (¥108 / 本)新品最安値 :¥864 (¥108 / 本) 炭酸水発売日 : 2018年04月24日価格 : ¥2,073 (¥86 / 本)新品最安値 :¥2,073 (¥86 / 本)
炭酸水発売日 : 2018年04月24日価格 : ¥2,073 (¥86 / 本)新品最安値 :¥2,073 (¥86 / 本) ミネラルウォーター発売日 : 2025年03月04日価格 : ¥1,898 (¥79 / 本)新品最安値 :¥1,898 (¥79 / 本)
ミネラルウォーター発売日 : 2025年03月04日価格 : ¥1,898 (¥79 / 本)新品最安値 :¥1,898 (¥79 / 本)
 機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥3,800新品最安値 :¥3,800
機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥3,800新品最安値 :¥3,800 機種別発売日 : 1970年01月01日For Xbox Series S収納バッグ,シリーズゲームコンソールと互換性のあるハードキャリングケースワイヤレスコントローラーおよびアクセサリ用トラベルストレージバッグ 軽量 耐衝撃 持ち運び便利価格 : ¥3,900新品最安値 :¥3,900
機種別発売日 : 1970年01月01日For Xbox Series S収納バッグ,シリーズゲームコンソールと互換性のあるハードキャリングケースワイヤレスコントローラーおよびアクセサリ用トラベルストレージバッグ 軽量 耐衝撃 持ち運び便利価格 : ¥3,900新品最安値 :¥3,900 機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥9,905新品最安値 :¥9,905
機種別発売日 : 1970年01月01日価格 : ¥9,905新品最安値 :¥9,905 機種別発売日 : 2024年05月24日価格 : ¥17,980新品最安値 :¥17,980
機種別発売日 : 2024年05月24日価格 : ¥17,980新品最安値 :¥17,980 ブースターパック発売日 : 2025年11月28日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500
ブースターパック発売日 : 2025年11月28日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500 ブースターパック発売日 : 2026年02月28日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775
ブースターパック発売日 : 2026年02月28日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775 ブースターパック発売日 : 2026年03月20日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775
ブースターパック発売日 : 2026年03月20日価格 : ¥5,775新品最安値 :¥5,775 ブースターパック
ブースターパック ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,280新品最安値 :¥5,280
ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,280新品最安値 :¥5,280 ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,808新品最安値 :¥5,808
ブースターパック発売日 : 2026年01月31日価格 : ¥5,808新品最安値 :¥5,808 ブースターパック
ブースターパック ブースターパック発売日 : 2024年12月06日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500
ブースターパック発売日 : 2024年12月06日価格 : ¥5,500新品最安値 :¥5,500 ブースターパック
ブースターパック ブースターパック
ブースターパック ブースターパック発売日 : 2025年11月22日価格 : ¥5,635新品最安値 :¥6,200
ブースターパック発売日 : 2025年11月22日価格 : ¥5,635新品最安値 :¥6,200 ブースターパック発売日 : 2025年10月18日価格 : ¥3,400新品最安値 :¥3,400
ブースターパック発売日 : 2025年10月18日価格 : ¥3,400新品最安値 :¥3,400 ブースターパック発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥11,300新品最安値 :¥10,500
ブースターパック発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥11,300新品最安値 :¥10,500 ブースターパック発売日 : 2025年12月20日価格 : ¥5,555新品最安値 :¥5,500
ブースターパック発売日 : 2025年12月20日価格 : ¥5,555新品最安値 :¥5,500 ブースターパック発売日 : 2025年10月25日価格 : ¥4,430新品最安値 :¥4,430
ブースターパック発売日 : 2025年10月25日価格 : ¥4,430新品最安値 :¥4,430 ブースターパック発売日 : 2025年03月15日価格 : ¥2,891新品最安値 :¥7,390
ブースターパック発売日 : 2025年03月15日価格 : ¥2,891新品最安値 :¥7,390
 ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥6,980新品最安値 :¥6,980
ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥6,980新品最安値 :¥6,980 ストリーミングデバイス発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980
ストリーミングデバイス発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980 タブレット発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980
タブレット発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980 メディアストリーミング端末発売日 : 2025年10月15日価格 : ¥9,980新品最安値 :¥9,980
メディアストリーミング端末発売日 : 2025年10月15日価格 : ¥9,980新品最安値 :¥9,980 ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥2,980新品最安値 :¥2,980
ストリーミングデバイス発売日 : 2024年10月22日価格 : ¥2,980新品最安値 :¥2,980 メディアストリーミング端末発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥7,980新品最安値 :¥7,980
メディアストリーミング端末発売日 : 2025年11月14日価格 : ¥7,980新品最安値 :¥7,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥27,980新品最安値 :¥27,980
電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥27,980新品最安値 :¥27,980 スマートスピーカー発売日 : 2023年02月14日価格 : ¥7,480新品最安値 :¥7,480
スマートスピーカー発売日 : 2023年02月14日価格 : ¥7,480新品最安値 :¥7,480 スマートスピーカー発売日 : 2023年05月31日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980
スマートスピーカー発売日 : 2023年05月31日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980 タブレット発売日 : 2024年10月02日価格 : ¥15,980新品最安値 :¥15,980
タブレット発売日 : 2024年10月02日価格 : ¥15,980新品最安値 :¥15,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980
電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥19,980新品最安値 :¥19,980 オーディオ・スピーカー発売日 : 2024年07月08日価格 : ¥11,480新品最安値 :¥11,480
オーディオ・スピーカー発売日 : 2024年07月08日価格 : ¥11,480新品最安値 :¥11,480 スマートスピーカー発売日 : 2023年08月08日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980
スマートスピーカー発売日 : 2023年08月08日価格 : ¥12,980新品最安値 :¥12,980 電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥32,980新品最安値 :¥32,980
電子書籍リーダー発売日 : 2024年10月16日価格 : ¥32,980新品最安値 :¥32,980 電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥44,980新品最安値 :¥44,980
電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥44,980新品最安値 :¥44,980 スタンダード型防犯カメラ発売日 : 2023年06月08日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980
スタンダード型防犯カメラ発売日 : 2023年06月08日価格 : ¥5,980新品最安値 :¥5,980 電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980
電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980 電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980
電子書籍リーダー発売日 : 2025年07月24日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980 電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980
電子玩具・キッズ家電発売日 : 2023年10月18日価格 : ¥23,980新品最安値 :¥23,980 スマートスピーカー発売日 : 2025年11月12日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980
スマートスピーカー発売日 : 2025年11月12日価格 : ¥39,980新品最安値 :¥39,980
靴底のすり減り補修ゴムの交換のやり方
⑴かかとを補修ゴムを剥がす
▼写真左側の補修プレートが特に摩耗しており、最も削れているところで厚み1㎜もない状態です
靴を脱いだ時に靴裏を見る習慣をつけると本体に侵食する前に気付くことができます

両面テープタイプの補修プレートは、素手で外せます。
靴用ボンドを使用した場合は、釘抜きの工具をソールと補修ゴムの間に差し込んで鍵を抜きます。
ニューキストは、元々両面テープですが個人的に剥がれにくくするために両面テープを剥がして靴用ボンド(靴・革・ゴム用の接着剤)を使用しています。
SUMCOは、両面テープタイプと靴用ボンド付タイプがあります。
⑵ソールに付着したテープや靴用接着剤を取り除く

ソールに残ったテープやボンド・汚れ・砂などの凹凸があると交換した補修ゴムが剥がれやすいです。
靴に汚れがあるときは、除光液やアセトンを1〜2滴ほど染み込ませたコットンや綿棒で拭くと落ちやすく補修ゴムも貼りつきやすくなります。
ただし、アセトンや除光液は樹脂や塗装を溶かすため生地に付くと剥げたり、変色するおそれもあります。取り扱いにご注意ください。
※アセトン、除光液、アルコールなどをご使用の際は火気厳禁です。揮発性が高いため作業中の部屋の換気が必須です
画像のように溝に残った汚れやボンドは、爪楊枝・歯ブラシ(かため)・靴用ブラシ・たわしなどで粗方取り除きます。
▼毛先がギザギザなビトイーン(山型の歯ブラシは歯と歯の隙間を磨きやすい)
▼毛先が平らなGUM(平らな歯ブラシは圧力が均等にかかりやすく歯垢が溜まりやすい歯と歯肉の間を磨きやすい)
平らな歯ブラシは、靴の溝やタイルの溝など細いところの掃除にも使いやすいです。

ソールの凹凸が全体的にすり減ったり、つなぎ目付近にひび割れが少し見受けられますが、かかと部分は補修プレートを定期的に交換し続けていると形を保てます。
⑶砂やほこりを洗い流して乾かす

▲エヌケーのシューズハンガーは向きを変えれるので水切りに便利
埃や砂を落として接着しやすくするために靴を洗って、しっかりと乾かします。
補修プレートを貼り付けて釘を打ち込む

▲空き缶を裏向きに差し込むと鍵を打ち込みやすくなります
✔︎両面テープの場合:フィルムを剥がして貼り付けてから釘を打ち込む
✔︎靴用ボンドの場合(塗るコツ):補修プレート側に靴用接着剤を薄めに塗ります。
アウトソールに押し付けると接着剤の液が伸びるため0.5〜1㎜くらいの余白を残しています。
薄〜く伸ばした時はあまり余白は必要ないですが、液の量が多いとはみ出ます。お好みで調整してください。
▼100均の透明な靴用ボンド

▼プロの修理屋さんも使うダイアボンド(黄淡色)

通販で買える靴用専用接着剤には、ノガワケミカル株式会社「ダイアボンド(靴・皮革・ゴム用)」やテラオ株式会社「SHOE REPAIR KIT(皮革用接着剤) ※瞬間接着剤ではない方のタイプ」などがあります。
硬化にかかる時間は約10〜20分/硬化後も柔軟性がある/液の色は、どちらも黄淡色(半透明で薄い黄色)
100均の靴用ボンド、ゴム用のエポキシ樹脂、ゴム用ボンドなどに透明色なものも存在します。
接着するまで指で押さえつけながら硬化を待ちます。
速乾性の靴用瞬間接着剤の場合は、鍵を打ち付けてる最中に固まってしまうおそれがあるので硬化してから釘を打ち付けた方が仕上がりが綺麗です
※接着剤が手につかないように使い捨てのビニール手袋を使用してください
※接着剤の蓋を閉めるときは、フチに垂れた接着剤を綺麗に拭き取らないと蓋がしっかりと閉まらずに空気に触れて使わないうちに固まってしまいます

釘打ちタイプの補修プレートは、靴裏の溝が深い靴やかかとの反りが大きいものには不向きです。
補修プレートには靴の踵が平らで溝が浅いものに向いているため、新しく靴を購入するときはアウトソールを確認してください。
両面テープの場合は、釘を打ち込んで完了です。
靴用ボンドの場合は、完全に硬化するまで時間がかかるため補修プレートを付けた当日の使用を避けた方が無難です。
体験談:使用感想
- 補修ゴムを付ける場合は、新品の靴に付ける方が剥がれにくい
- 本体のソールがすり減った状態では隙間が出来やすく剥がれやすくなる
- ソールが少し反っていて平らではない場合は、予め補修ゴムを曲げてソールのカーブに合わせる(反りが大きいものには使えない)
- 靴のサイズが合っていなかったり、靴紐が緩すぎて靴が足にフィットしていない状態での歩行は、踵を地面に引きずりやすいため剥がれやすく摩耗が早まる
- 補修プレートの厚みや歩く距離、歩き方、歩く場所にもよりますが、週2回程度の使用頻度であれば2〜3回の交換で約1年ほど本体の踵のすり減りを防げる
- 道路わきの排水用の溝の上においてある表面がギザギザの鉄板、砂利道、段差などで補修プレートを引っかけてしまうと剥がれることがあります
- 靴底の確認を怠ってしまうと本体の踵のソールがすり減ってしまうため定期的に確認する
- ニューキストとSUMCOを比較すると、SUMCOの方が硬い質感で少し厚め、ニューキストの方が薄く柔らかめです
- 補修プレートを付けるようになって無残にすり減った靴が減って頼もしい
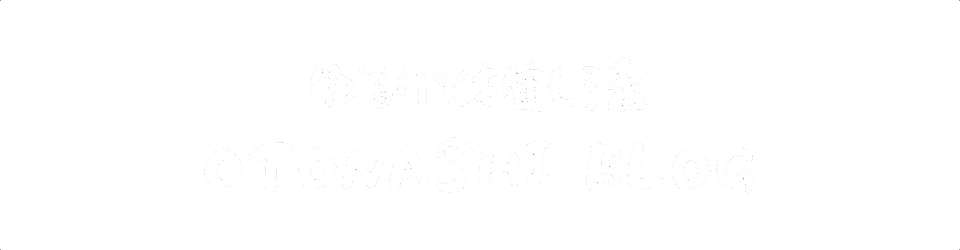





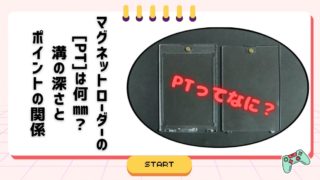
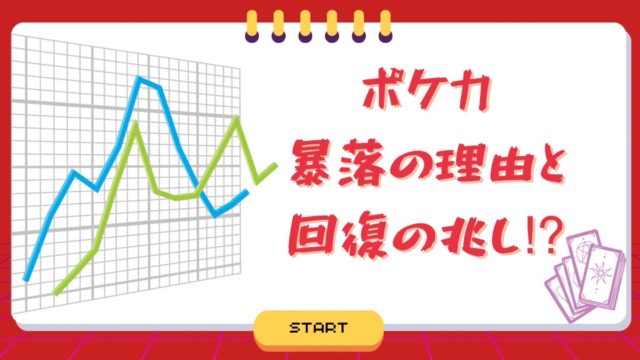

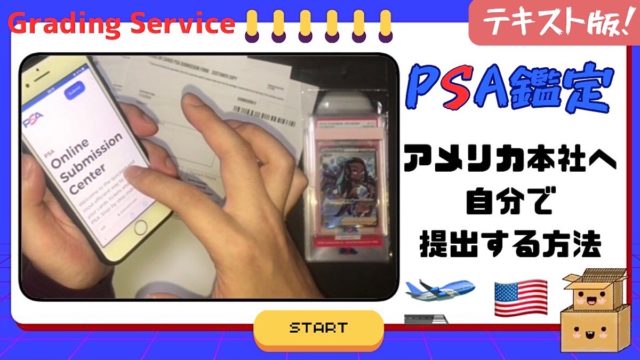

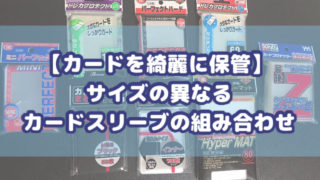

![[ロイヤルリビング] New KIST(ニューキスト) 靴修理キット・カカト用(2足分) SIZE:2~4](https://m.media-amazon.com/images/I/416S78LJKLL._SL160_.jpg)


















































































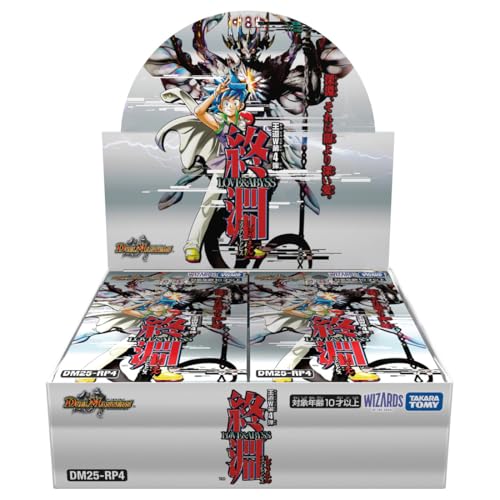








































![GUM(ガム) デンタル 歯ブラシ#191 [3列超コンパクトヘッド かため 先細毛] 6本パック+おまけ付き まとめ買い ※色は選べません](https://m.media-amazon.com/images/I/513sSZgslbL._SL160_.jpg)


























